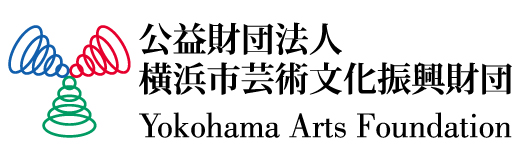演奏だけではないホールオルガニストのお仕事
ひとつは“楽器のメンテナンス”
日本でパイプオルガンを備えるコンサートホールは多くありますが、すべてのホールに専任のホールオルガニストがいるわけではありません。
「アドバイザーというポジションの方がいらっしゃるところもありますが、ホールオルガニストほど、日常的に密接にパイプオルガンに関わってはおられないようです。専任のホールオルガニストがおらず、ときどきオルガニストが招かれるだけという場合には、そのオルガニストが不具合に気づくしかないのですが、日頃からその楽器を見ているわけではありませんので、なかなか大変だと思います」
「ルーシー」という愛称で親しまれる、横浜みなとみらいホールのパイプオルガンは手鍵盤が3段と足鍵盤が1段、ストップ(音栓)が62個、パイプの数は4623本と国内でも有数の規模を誇ります。これだけのパイプオルガンとなると構造も複雑で、特に最初の頃は、調子が悪くなることもあったそうです。
「パイプオルガンは、大小さまざまなパイプに空気を送り込むことで音が鳴り、ストップの選択・組み合わせによって非常に多彩な音色を生み出すことができます。ルーシーは62のストップを具えていますが、その組み合わせ方を内部のコンピューターに記憶させておくんですね。ところが、その記憶装置の不具合が、初期にはしばしばおきまして、そのたびに技術者に対応してもらいました。でも、次第に安定してほとんど問題はなくなりましたけれど」

写真左:3段の手鍵盤。ストップ(選んだものを引き出す)の組み合わせ(レジストレーション)を記憶させます
写真右:足鍵盤。オルガン靴はかかとのある、演奏しやすいものを選んでいます
ホールオルガニストには、演奏者としてだけではなく、楽器のメンテナンスをするという大切な役割もあるといいます。
「パイプオルガンは多数のパイプや部品で成り立つ繊細な楽器ですから、日頃からメンテナンスが欠かせません。基本的には、楽器を安定した状態に保つため、月の半分程度、お客様のいらっしゃらない時間に弾き込みをします。その時間帯の確保がなかなか難しく、ホールスタッフとスケジュールをよく調べて空き時間を見つけます。このメンテナンスは、ただ片端から音を出していくのではなく、音楽としてさまざまな曲を演奏していく中で、不具合を発見する作業です。一人では弾ききれませんから、インターンやインターン修了生の手も借りています」