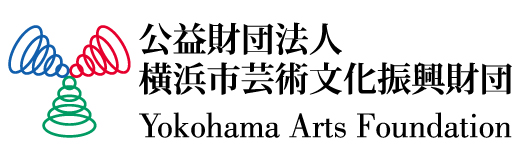自主事業責任者の新山久志さんに施設の特徴を伺うと、特に音楽ホールの音響に定評があるといいます。
「クラシックコンサートなど、楽器本来の響きを楽しむ演奏に適していて、年間貸し出し可能日のほぼ100%が利用されています。音楽ホールで隔月開催している『サルビアホール カルテットシリーズ』には、この音響の良さを楽しもうと、横浜市外や都内から足を運んでくださる方も多くいらっしゃいます」
そして、長年続くシリーズ企画が多いことも特色だと話してくれました。
「二ツ目の噺家さんによる『さるびあ寄席』とミニコンサートシリーズ『水曜音楽会』は、それぞれ隔月で交互に開催しています。どちらも開館当初からの人気企画で、地域の方々が楽しみにしてくださっています」

*2017年2月19日に音楽ホールで開催された「サルビアホール室内楽シリーズ ヴァイオリン大宮臨太郎『弦楽デュオ』」の様子
事業担当者の福田直樹さんは、各国の文化を“学ぶ”ことと“体験する”ことの両方ができるというワークショップのシリーズ「サルビア・アカデミー」について話してくれました。
「鶴見区は横浜市内で2番目に外国人が多く住んでいるということもあり、多文化共生を意識して始めたのがこのシリーズです。シリーズの名称は途中で変わっていますが、開館当初から年5~6回開催してきました。これまでに好評だったテーマは、『俳句』『カリンバ(アフリカの楽器)作り』『お香』『パチカ(アフリカの楽器)』などです。年に1回は、日本の文化を取り入れるようにしています」
リピーターの参加者も多いため、テーマの重複や繰り返しを避けるようにしているとのこと。多様な文化に関するテーマや講師を探すことや、背景や歴史の学習と体験の組み合わせ方などに苦労しながらも、地域の方々の興味に応える工夫をしてきた姿勢が、10年間つづいた秘訣だと感じました。

*2020年11月28日に開催された「サルビア・アカデミー #55 カリンバワークショップ」の様子
地域の特性に合って長年人気のシリーズである、この「サルビア・アカデミー」を実際に見学させていただきました。
取材に訪れた今年1月10日の「サルビア・アカデミー」は通算56回目の開催で、テーマは「狂言」。この日は募集定員いっぱいの18人が参加しました。今回は、サルビアホールと同じ建物内にある鶴見国際交流ラウンジも開催協力していて、外国人6人も参加しました。

講師は大蔵流茂山千五郎家狂言師の松本薫さん。松本先生の「狂言を観たことがない人は?」との問いかけに、7~8人の手が上がりました。そこで「狂言とは」の解説から始まり、その成り立ちを学びました。
次に扇が1本ずつ全員に配られて、「骨」「要(かなめ)」といった部分の名前を教わり、開き方と閉じ方の練習をしました。
そして、狂言における扇の役割を学びます。まずはお酒の注ぎ方から。掛け声は「それ、それ、そーれそれそれ」です。どういう所作をしたらこぼれないようにお酒を注いで、上手に受けて飲むように見えるか、日常的な身体の感覚を意識することが大切だと教わりました。
扇を使ったほかの所作–「ずか、ずかずか、ずっかり」と言いながらのこぎりを切る、「さらさらさらー」という掛け声で戸を開ける–もやってみました。会場のリハーサル室はだんだんとなごやかな雰囲気になってきました。

扇の種類によって身分や階級のちがいなどがわかることも知りました
今度は3cm×20cmくらいの細長い白い紙が全員に配られました。「平元結(ひらもっとい)」という髪飾りを折って作る体験です。女の人やこどもの髪を結ぶ髪飾りなのですが、舞台のたびに毎回手作りするそうです。ひっくり返したり輪にしてくぐらせたりとかなり複雑な手順なので、参加者も皆真剣な表情です。
1時間半のワークショップの終わるころには、扇の使い方や演技のしかた、髪飾りを作る体験を通して、狂言にいっそう興味がわいてきたようです。松本先生も「ぜひ狂言の舞台を実際に観て、どういうふうに所作や身体の動きを生かしているかをよく見てほしい」と話して終了となりました。
参加者の方に感想をお聞きしてみました。

「さらさらさらー」と言いながら戸を開けて家の中を覗く所作を体験する、曹閎博(そう・ほんぼ)さんと藤井文さん親子
中国から2年前に日本に来た曹閎博(そう・ほんぼ)さん(中学2年生)と藤井文さん親子は、時々相談やイベントのために来ている鶴見国際交流ラウンジですすめられて参加したそう。「狂言のことはまったく知らなかったのですが、先生の説明がとてもわかりやすくて、日本の文化に興味津々となり、楽しい時間を過ごせました」

紙を折って「平元結(ひらもっとい)」を 作る体験をする、茅根さくらさんと優人さん
旭区から来た茅根さくらさん(11歳)と優人さん(9歳)の姉弟は、お母さんからすすめられて参加しました。2年前に別の施設が実施した狂言のワークショップに参加したことがあり、今回の参加を楽しみにしていたそうです。「扇ひとつでいろいろな動作ができることを体験しておもしろかった」「また来たいです」と話しました。
ワークショップを終えて福田さんは、
「今日の参加者のように、狂言をまったく知らない外国の方もいらっしゃるのがこの館の特色です。一方で松本先生のファンの方もいらして、知識と興味の度合いがバラバラなので、誰もが満足していただける内容を提供するのはかなり難しいのですが、講師の方としっかりと打ち合わせをしています。今日はコロナ対策のため普段とは違う場面もありましたが、参加者の笑い声や『勉強になった』『楽しかった』というご感想が聞けてホッとしています」と話してくれました。
開館10周年を迎えるサルビアホールですが、最後にこれからの活動について新山さんに伺いました。
「鶴見区は人口が増加している区で、最近は新興住宅地に転入してくる子育て世代が急増しているので、乳児や子ども、親子に向けコンサート『さるびあおんがくひろば』などに力を入れてニーズに応えていきたいです。また、鶴見区内で活動するNPO法人や芸術文化団体といった地元の団体との連携をいっそう強めることや、鶴見区内の地区センターなどの地域コミュニティとの協力関係をより密にしていきたいです」
サルビアホールには、国際色豊かで多文化な人々のニーズ、急増している子育て世代のニーズといった地域の特性に応えて、地域の多様な人々に愛される場所を目指している姿がありました。

サルビアホールが入る商業施設「シ―クレイン」の外観(写真左)とサルビアホールの受付(写真右)
●Information
横浜市鶴見区民文化センター「サルビアホール」
➤アクセス JR京浜東北線・鶴見線「鶴見」駅 東口から徒歩2分
京急本線「京急鶴見」駅 西口から徒歩2分 シークレイン内
➤WEBサイト http://www.salvia-hall.jp/
●Event
横浜市鶴見区民文化センター「サルビアホール」でこれから開催されるアートイベントはこちら
サルビアホール近くのおすすめスポット
御菓子司 清月

サルビアホールとご近所のこちらの和菓子屋さんは1910年(明治43年)の創業。東海道の鶴見名物としても名高かったもののすっかり忘れ去られていた「よねまんじゅう」は1982年にモダンなアレンジで復活をとげました。薄く伸ばした羽二重餅に白餡、こし餡、梅餡の3種類の餡をくるんだお菓子は神奈川名菓100選にも選ばれ鶴見名物として親しまれています。
➤WEBサイト http://seigetu.nl.shopserve.jp/
※営業時間など詳細は、公式WEBサイトをご確認ください

写真左:よねまんじゅう / 写真右:打菓子ルナ・ピエーナ